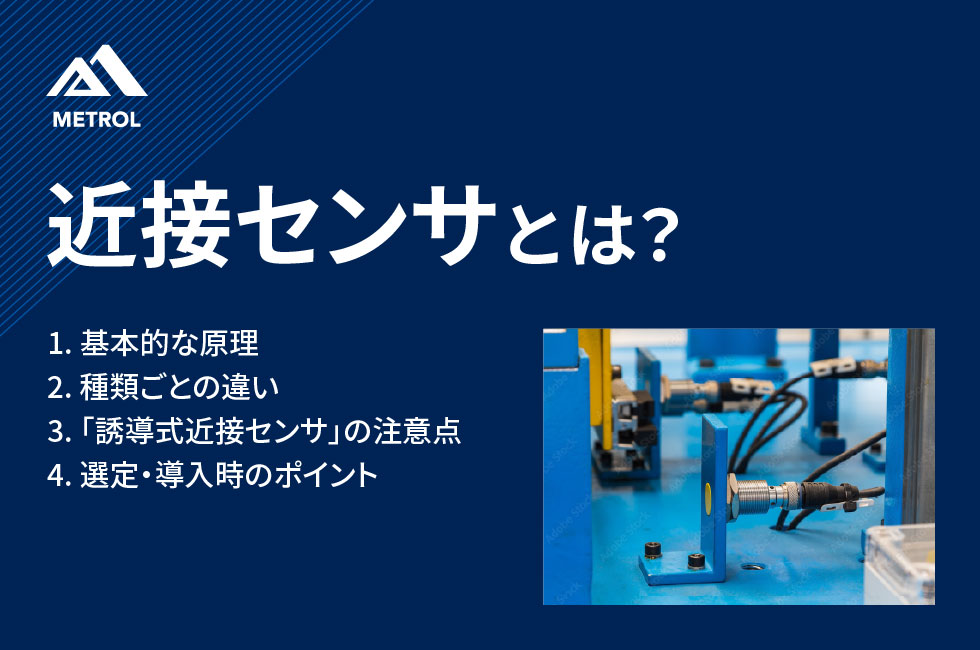センサの種類とは?センサの原理や製造業での活用まで

温度や光などの物理現象を電気信号に変え、機械に「五感」を持たせるセンサは、スマホや自動車からスマートファクトリーまで幅広く活躍しています。
本記事では、センサの概要と種類、製造業への活用方法について解説します。
目次
センサとは何か?

センサとは、温度や光などの物理的な現象を検知して電気信号に変換する装置です。
例えば温度センサであれば周囲の温度を感知し、それに応じた電圧や電流を出力します。
つまり、入力(物理量)としての環境の変化を捉え、対応する出力(電気信号)に変えるためのデバイスです。
私たちの身のまわりには多くのセンサが使われており、たとえば温度、光、音、圧力、動きなど、さまざまな「変化」を捉えることができます。
多くのセンサは内部にこうした変換の仕組みを備えており、人間にとっての「五感」のように機械に外界の情報を与えます。
日常生活に欠かせないセンサの役割

センサは私たちの生活に深く溶け込んでおり、日々の暮らしの中で欠かせない存在となっています。目には見えないものの、私たちの身の回りには数多くのセンサが搭載されており、安全性や快適性を支えています。
例えば、スマートフォンの画面が周囲の明るさに応じて自動調整されるのは、光センサの働きです。自動ドアが人の動きを検知して開くのは人感センサ、自動車の衝突防止機能には加速度センサや距離センサが使われています。
このように、センサは私たちの「目・耳・肌感覚」のように環境の変化を感じ取り、機械や電子機器にとっては目や耳のような役割を果たします。
要するに、センサは外界の状態を正確に把握し、それを機械が理解できる形に変換する橋渡し役なのです。
現代の便利で安全な生活は、センサ技術の発展によって支えられているといっても過言ではありません。
センサの主な種類と特徴
センサには、検出する対象に応じて様々な種類があります。代表的なセンサの種類とその特徴を以下に紹介します。
温度センサ

周囲の温度を測定するセンサです。
例として、サーミスタ(温度によって抵抗値が変化する半導体素子で高感度・小型)、熱電対(異なる金属の接点に生じる熱起電力を利用し広範囲の温度に対応)、測温抵抗体RTD(金属の抵抗変化を利用し特に白金製は安定性が高く高精度)などがあります。
用途としては、電子機器の温度監視やエアコン・冷蔵庫の温度制御、産業用の温度管理まで幅広く使われています。
光センサ

光の強さや波長を検知して電気信号に変換するセンサです。
例として、フォトダイオード(受けた光の強さに応じて電流を発生し高速応答)、フォトトランジスタ(光によって生じる電流を増幅できるため高感度)、CCD/CMOSイメージセンサ(デジタルカメラなどで使われ、高解像度の画像を取得可能)などがあります。
また、人の体から放射される赤外線を検知するモーションセンサも光センサの一種であり、自動照明や防犯システムに利用されています。
加速度センサ

物体の加速度(速度の変化)を検出するセンサです。スマートフォンやゲームコントローラー、車のエアバッグ制御などに広く搭載されており、微小な機械構造を持つMEMS技術(Micro Electro Mechanical Systems:微小電気機械システム)によるものが主流です。
MEMSを用いることでセンサが非常に小型化され、高感度・高精度に傾きや振動、衝撃を検知できます。製品によってはジャイロセンサを組み合わせて回転まで検出できる多軸加速度センサも存在します。
圧力センサ

気体や液体の圧力(押す力の強さ)を測定するセンサです。例えば工場の配管内の圧力監視や、自動車のタイヤ空気圧モニタリング、血圧計などに利用されます。
原理の違いによって、ピエゾ抵抗型(圧力により内部素子の電気抵抗が変化する現象を利用し高感度)や容量型(圧力でセンサ内部の電極間距離が変わり静電容量が変化する原理で安定性が高い)などの種類があります。
また、金属に加わる歪みによる抵抗変化を測るひずみゲージを用いた圧力センサもあり、大きな荷重を測定するロードセル(重量計)として応用されています。
近接センサ

物体に触れることなく、一定の近さに対象物が来たことを検出するセンサです。
対象の有無や位置を非接触で感知できるため、工作機械の位置決めや自動ドアの人検知、スマートフォンの画面オンオフ(耳に近づけた際に画面を消灯する機能)等に利用されます。
例えば金属物体に反応する誘導型(電磁誘導によって金属中に発生する渦電流の影響でコイルのインピーダンス変化を検出)や、金属以外も検出可能な静電容量型(センサと対象物との間の静電容量の変化を検出)などが代表的です。
この他にも超音波や赤外線を利用して物体までの距離を測る近接センサもあり、用途に応じて使い分けられます。


センサの基本構造と動作原理

センサは一般に、内部で「検出→変換→出力」という3つのステップを踏んで動作します。以下は典型的なセンサの構成要素です。
| 構成要素 | 役割(機能) |
|---|---|
| 検出部 | 測りたい物理量を直接感知する部分(センサ素子)。例えば熱、光、力などを受け取る。 |
| 変換部 | 検出部で感知した物理量の変化を電気信号に変える部分。例:抵抗値の変化を電圧に変換する回路など。 |
| 出力部 | 得られた電気信号を外部の機器に出力する部分。アナログ信号やデジタル信号としてマイコン等に送られる。 |
上記のように、センサ内部ではまず物理量の変化を捉え、それを何らかの電気的な変化(電圧・電流・抵抗など)に置き換えて出力しています。
例えば、温度センサでは温度変化によって内部素子の抵抗値が変わり、その抵抗変化が電気回路で電圧の変化として読み取られます。
同様に圧力センサでは、圧力によって素子の抵抗が変わるものや、圧力で電極間の距離が変化して静電容量(コンデンサの容量)が変わる原理のものがあります。
このようにセンサごとに様々な変換原理が使われていますが、基本的には「物理現象の変化を電気的な信号(数値)に変える」という点で共通しています。
また、センサの出力はアナログ信号(連続的な電圧や電流)である場合と、内蔵マイコンなどでデジタル値に変換して出力する場合があります。後者は通信方式によっては直接マイコンとデータをやり取りでき、ノイズに強い利点があります。
センサ動作原理の具体例
センサの原理を一つ例を挙げて説明します。先述の加速度センサ(MEMS式)の場合、小さなチップの中に重り(質量)とバネで構成された微細な構造体があります。
静止時にはバネは中立の位置ですが、加速度が加わると重りがわずかに動き(バネが伸び縮みし)ます。この動きによって、センサ内部では例えば重りに付随する電極間の距離が変化し、静電容量(電気的な容量)の値が変わります。
センサ回路はこの容量の変化を検出し、それに対応する電圧信号を出力します。重りの変位の大きさは加速度に比例するため、この電気信号を解析することで加えられた加速度の大きさがわかる仕組みです。
MEMS加速度センサでは他にも重りにかかるひずみで抵抗値が変化する方式(ピエゾ抵抗式)などがありますが、いずれも機械的な動きを電気信号に変換している点は共通しています。
このような微小な構造を半導体チップ上に作り込むMEMS技術により、加速度センサは極めて小型で安価に量産でき、スマートフォンのようなデバイスにも搭載可能です。
製造業におけるセンサの重要性

近年、製造業ではスマートファクトリーやIoT(モノのインターネット)、インダストリー4.0といったキーワードのもとでセンサ技術が飛躍的に重要性を増しています。
インダストリー4.0(第4次産業革命)とは、工場内のあらゆる設備やセンサをインターネットでつなぎ、収集したデータを活用して生産性の向上や新たな価値創造を実現しようとする世界的な取り組みです。
実際、工場の機械や製品に多数のセンサを取り付けてデータを集め分析することで、生産工程の最適化や人手不足・技能継承といった多岐にわたる課題を同時に解決できる可能性が示されています。
このようにセンサを活用したデータ主導での改善は、製造業のデジタル化における基盤となっています。
センサを活用した品質管理体制の強化

工場の各工程にセンサを配備し、温度・湿度・圧力・速度など製造プロセスの状態を監視することで、製品の品質を高精度に管理できます。
たとえば、画像認識カメラ(画像センサ)や各種IoTセンサを組み合わせれば、生産ライン上で製品の寸法や外観を自動検査し、不良品や異常を即座に検知してその場で取り除くことが可能です。
人間の目に頼っていた検品作業もセンサとAIによる自動化で効率化でき、ヒューマンエラーの削減や品質ばらつきの低減につながります。
生産性向上・予知保全への貢献
センサを用いた常時モニタリングは、生産性の向上や設備のダウンタイム短縮にも威力を発揮します。
機械の振動や温度、電流値などを24時間監視し、そのデータを解析することで、異常の兆候を早期に発見して故障を未然に防ぐことができます。
これを予知保全(予兆検知による保全)と呼び、従来の定期点検や事後対応に代わって注目されています。
例えば、ある自動車部品工場ではIoTセンサを使い工作機械の回転数や温度をリアルタイム監視し、通常と異なる振動や温度上昇を検知した段階でメンテナンスを行う仕組みを導入しています。


加工現場の実務者から見たセンサの事例と役割
一台の工作機械の中には数多くのセンサが取り付けられており、稼働する箇所や役割によって使い分けがされています。
工作機械で使われているセンサの主な役割について、解説していきます。
センサは機械の正常動作をサポートする安全装置である
工作機械にとってセンサは必要不可欠なものであり、機械加工の現場で作業する方々の安全を守ったり、生産される製品の品質を確認したりするために役立っています。
また、ヒューマンエラーによる事故を未然に防ぎ、異常な過負荷や熱暴走による機械本体の故障から「機械本体」を守るために他種多様なセンサが常時稼働しているので、従事する作業者は安全で安定した生産が可能です。
センサが正常に稼働しているおかげで、人間では気づかないようなパレットの微妙な着座不良を未然に回避できるので、剛性不足によるビビりや位置ずれによる加工不良、工具の衝突から製品を守れます。
自動工具交換でも、稼働範囲内に多くのセンサが使われているので次のような危険から作業者を守っています。
- 動作未完了による工具の脱落
- 工具同士の衝突
- ATCマガジン動作中のアームの誤作動
- メンテナンスドア開錠時のマガジン誤作動
安全装置の取り付け・設計では「フールプルーフ」の考え方が基本

こういった機械にセンサを取り付ける際は「フールプルーフ」の考え方を基本にします。
「フールプルーフ(foolproof)」とは、人間(知識のない人)が誤操作・危険な行動をしても大きな事故や問題に発展しないよう、事前に設計や仕組みで対策しておくというやり方です。
フールプルーフは「愚か者に耐える」という意味を持ち、人為的なミスを未然に防ぐための考え方で、工作機械に限らず一般の家電製品や自動車などでも採用されています。
フールプルーフを採用したセンサ取り付け・設計の基本となる目的は「安全性を高め、ヒューマンエラーによる事故やトラブルを防止する」ことです。
- 近年の洗濯機は、ふたを開けたままでは洗濯を開始しない
- 自動車は、ブレーキを踏んでいないとエンジンがかからない
- オートバイは、サイドスタンドを出したままだとエンジンがかからない
- 電子レンジは、扉を開けたままだと加熱を開始しない
- エレベーターの扉は、閉まるときに障害物があると再度開く
- エレベーターの扉は、完全に閉まらないと上昇・下降しない
といった機能は「フールプルーフ」の考え方からきており、センサにより危険防止はこのような観点と同じ目的で採用されています。
加工機で活用されるセンサの事例
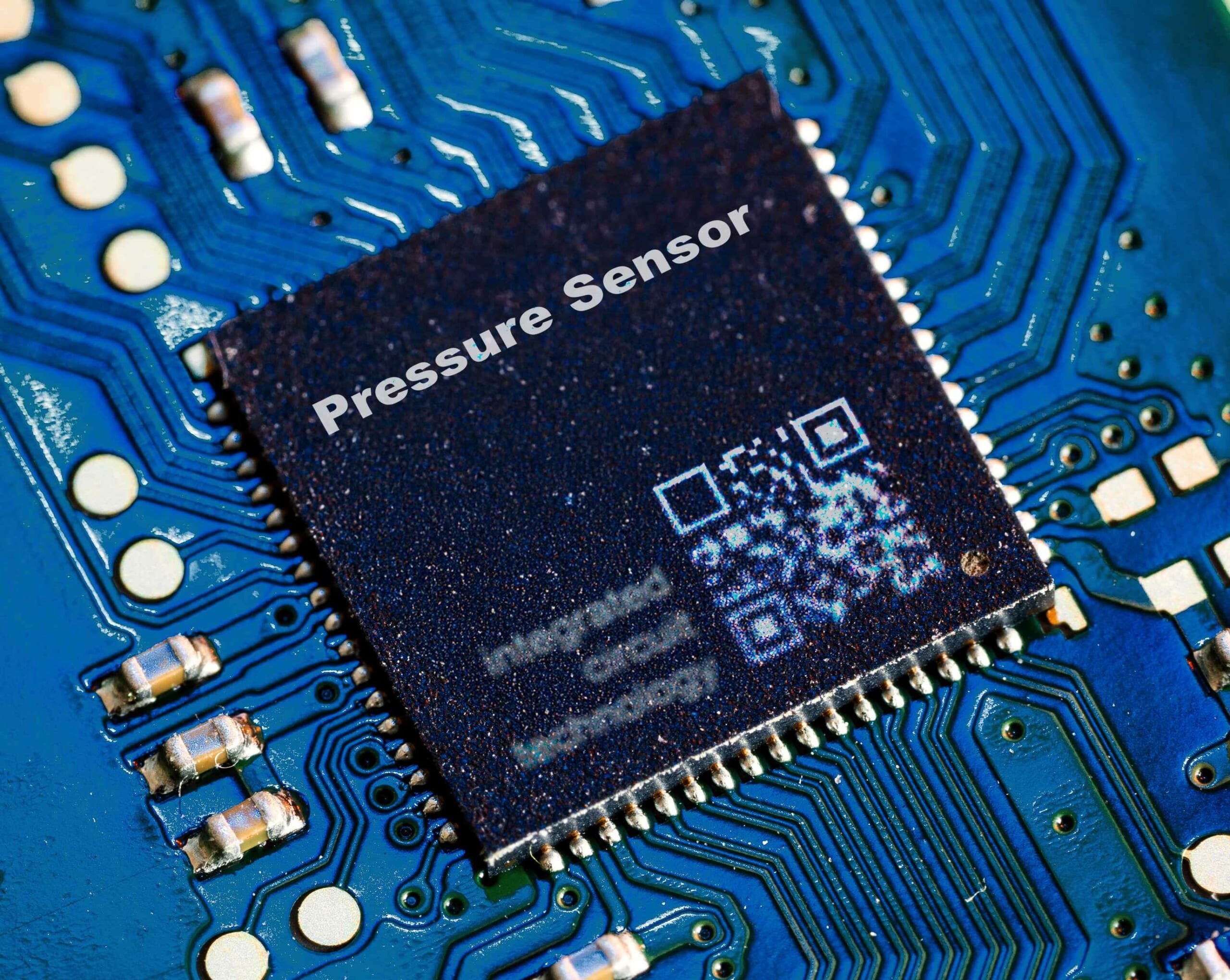
センサが使われているのは、パレットチェンジシステムやドアの自動開閉、機内の自動工具交換などが行われる「ワークスペース」だけではありません。
工作機械の主軸内部や駆動装置、制御盤内でも多様なセンサが使われており、過負荷による故障や熱による不具合などから機械本体を保護しています。
例えば、夏の暑い時期に機械の潤滑油・冷却水が不足すると「機械本体の異常過熱」が発生した場合、熱センサによる機械停止の信号(指令)がないと熱による加工不具合や制御盤内の基板の破損、摺動面やモーターの焼き付きが発生する可能性があり大変危険です。
そうなると、復旧にかかる時間や手間・コストが莫大なものになるだけでなく、顧客や製品の流通にも多大な損失・影響が発生します。
センサは、人間による判断が難しい判別も補助してくれる大切な装置です。
常にセンサを正常に作動させるためにも、日頃のメンテナンスや清掃などでセンサの位置や種類を把握しておき、汚れなどによる誤作動が起きないようにしておきましょう。
メトロールの高精度な位置決めセンサとは?
ここまで温度・光・圧力など多彩なセンサの種類を見てきましたが、製造や加工現場で特に重要になるのが位置を誤差なく測るためのセンサです。ミクロン単位で刃先やワークを狙い通りに合わせられるかどうかが、品質と歩留まりを大きく左右します。 その高精度な位置決めを支える専門メーカーであるメトロールの各種センサ製品を紹介します。
高精度位置決めタッチスイッチ(位置決めセンサ)
接触式の高精度スイッチで、工作機械やロボット、治具などの位置決めやワーク有無検出に用いられます。最大繰返し精度0.5µmと極めて高精度で、IP67の防水防塵性能を備え、悪環境下でも安定動作します。200種類以上の標準モデルがあり、狭所対応、高温対応、真空対応、低接触力タイプなどバリエーションが豊富です。
ツールセッタ(工具長測定センサ)
CNC工作機械や産業用ロボットに搭載し、工具長の測定や原点位置出し、工具折損検知などに使用される接触式センサです。工具の長さや摩耗、熱変位を機内で自動測定・補正することで加工不良を防止し、段取り時間を大幅短縮します。世界74ヵ国で50万台以上の出荷実績があるメトロールのベストセラー製品です。
タッチプローブ(機上測定プローブ)
工作機械やロボットに搭載し、加工前のワーク位置決め(芯出し)や加工後の寸法測定を自動で行う機内計測用の接触式プローブです。繰返し精度1µmでワークの基準出し・寸法検査を自動化し、熟練者の手作業を置き換えることで段取り時間短縮や加工不良防止に貢献します。有線式と無線式(ワイヤレス)のモデルがあり、5軸加工機やロボットへの後付けニーズにも応えています。
エアマイクロセンサ(空圧式センサ)
空気圧を利用した非接触センサで、ワークの着座状態を数ミクロン精度で検出できます。従来は困難だった10µm以下の隙間(「浮き」)を±0.5µmの繰返し精度で検知し、ワークと治具の密着不良による加工不良や設備のダウンタイムの発生を防止します。半導体製造プロセスや精密部品のクランプ工程、研削盤の砥石位置合わせなどで活用され、国際標準のIO-Link通信にも対応したスマートセンサです。
関連記事
タッチプローブによる研削盤の「機上測定」とは?
【導入事例】3Dプリンタの造形精度が10倍アップ!タッチスイッチ導入事例
3Dプリンタでの造形不良。原因は「テーブルの歪み」でした。
これまで近接センサでは検出できなかった造形テーブルの歪みを接触式で高精度に計測することで、1層目の造形失敗の原因となるテーブルの歪みを補正することに成功しました。
3Dプリンタメーカーのご担当者様に直接取材し、採用の経緯や効果についてお話しいただきます。